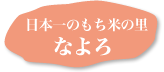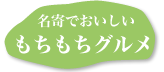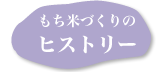1.日本の米作りのはじまり
 稲は日本列島に元から自生していた植物ではなく、縄文晩期から弥生初期にかけて、栽培方法とともに大陸から海を渡ってもたらされたものである。稲の原産地についてはインドのアッサム地方から中国雲南地方にかけての内陸部高原地帯と言われている。大陸から北九州に渡来した稲作は、青銅器や鉄器など大陸伝来の金属器とともに弥生時代に急速に普及。弥生中期には北海道と南西諸島を除くほぼ全国で稲作が行われるようになった。本州北端にまで広まった稲作であったが、北海道の寒冷な気候がそれ以上の北進を阻んだ。この時代の北海道は続縄文時代と呼ばれ、本州から鉄器は伝わっていたが、いまだ狩猟・漁労などの食糧採集を生業とし、土器も縄文土器を使用する独自の文化を歩んでいた。その後も江戸時代まで稲作が津軽海峡を越えることはなかった。
稲は日本列島に元から自生していた植物ではなく、縄文晩期から弥生初期にかけて、栽培方法とともに大陸から海を渡ってもたらされたものである。稲の原産地についてはインドのアッサム地方から中国雲南地方にかけての内陸部高原地帯と言われている。大陸から北九州に渡来した稲作は、青銅器や鉄器など大陸伝来の金属器とともに弥生時代に急速に普及。弥生中期には北海道と南西諸島を除くほぼ全国で稲作が行われるようになった。本州北端にまで広まった稲作であったが、北海道の寒冷な気候がそれ以上の北進を阻んだ。この時代の北海道は続縄文時代と呼ばれ、本州から鉄器は伝わっていたが、いまだ狩猟・漁労などの食糧採集を生業とし、土器も縄文土器を使用する独自の文化を歩んでいた。その後も江戸時代まで稲作が津軽海峡を越えることはなかった。
 北海道における米作りの始まりは諸説あるが、元禄5(1692)年、函館平野北部に位置する渡島国大野村(現・北斗市)の文月・押上地区において、野田作右衛門が450坪の水田から米10俵を収穫したのが最初とされる。その後も各地で試作されるが、なかなか定着しなかった。
北海道における米作りの始まりは諸説あるが、元禄5(1692)年、函館平野北部に位置する渡島国大野村(現・北斗市)の文月・押上地区において、野田作右衛門が450坪の水田から米10俵を収穫したのが最初とされる。その後も各地で試作されるが、なかなか定着しなかった。
明治2(1869)年、北海道に開拓使(現在の北海道庁)が設置され、家畜と畑作との欧米式混合農業を導入。北海道は寒冷地のため道南以外での稲作は不可能との判断であったが、島松村(現・恵庭市)に入植した中山久蔵が明治6(1873)年、大野村から耐寒品種「赤毛」の種もみを取り寄せ稲の試作に着手。水温が低くなかなか育たないため、苗代に風呂の湯を入れるなど様々な工夫と努力を重ね、より寒さに強い「赤毛」の改良を成功させた。久蔵が作った種もみは開拓農民に無償で配られ、石狩、空知、上川へと、北海道の米作りは広がっていった。